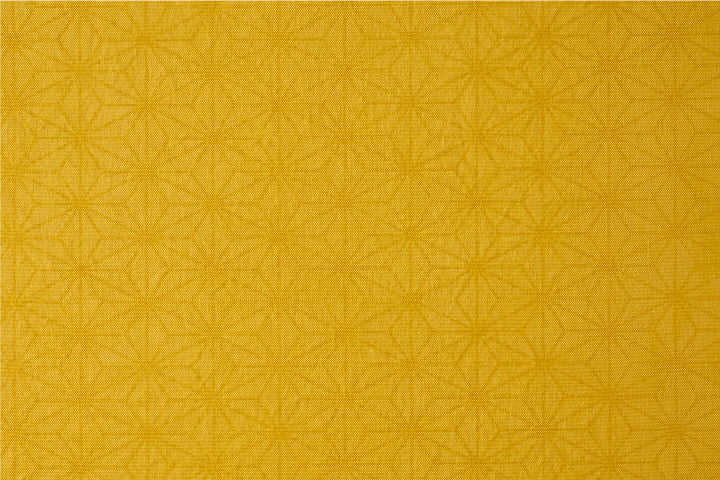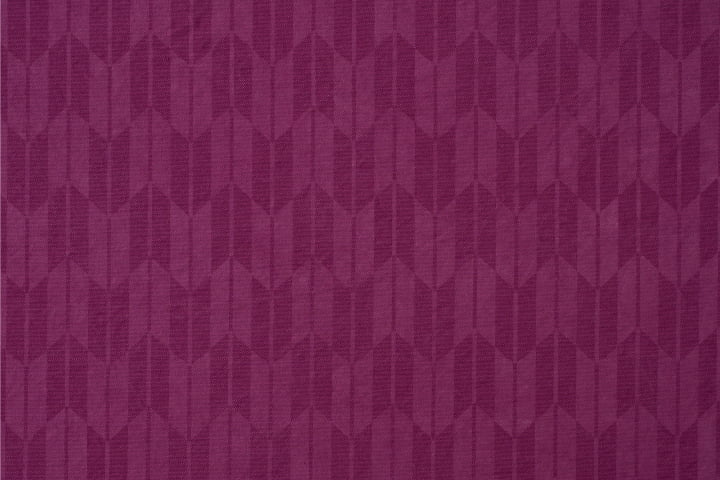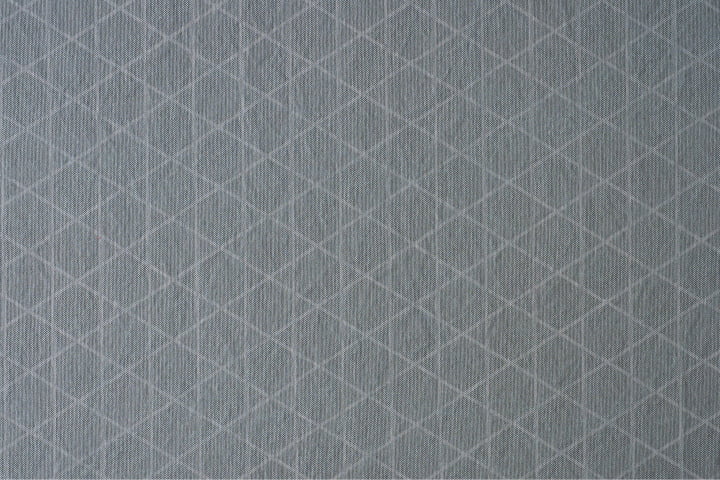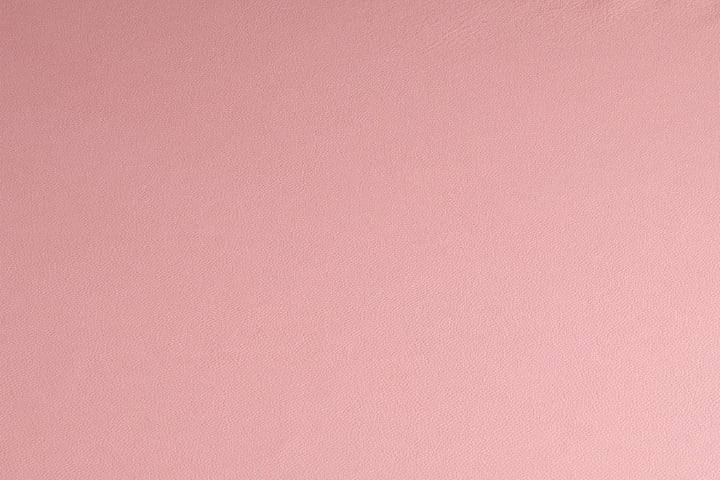素材について
wood
木材のStory
日本の国土の約7割は森林に覆われています。しかし、私たちの生活環境の変化により、これらの森林は今、深刻な危機に直面しています。近年、木材の多くを輸入に頼るようになったことで、国内の山々は適切な管理がされなくなり、環境の悪化が進んでいます。長年にわたり人の手が入らず放置された山は、本来の健全な姿を失いつつあります。私たちが使用している木材は、そうした環境問題の改善にもつながる、持続可能な資源です。森と人との関係を見つめ直し、未来のためにできることをかたちにしていきます。

1/fゆらぎ(エフブンノイチユラギ)
自然から生まれた癒しのデザイン
自然が生み出す木目には、「1/fゆらぎ」と呼ばれる波長が含まれており、私たちの心を落ち着かせ、安らぎをもたらすと言われています。この波長は、鳥のさえずりや川のせせらぎなど、自然界の音にも共通して存在しているとされ、人に心地よさを与えるリズムとして知られています。住宅の建材や自動車の内装に木目が多く用いられるのも、こうした効果を期待してのことです。また、木材が持つ多様な色合いや節の表情は、自然素材ならではの魅力であり、暮らしにささやかな喜びをもたらしてくれます。

活きた木とともに暮らしの中で
経年変化を楽しむ四季折々で使われる素材
数十年、数百年もの時を経た木は、家具となった後もなお、少しずつ表情を変えていきます。長く美しくお使いいただくためには、直射日光をできるだけ避け、水分や汚れにご注意いただき、清潔に保っていただけますと幸いです。木は年月とともに、色合いや明るさがゆるやかに変化していきます。それは、自然素材である木ならではの、時の流れを感じさせる魅力のひとつです。
木は暮らしに寄り添いながら、温もりと風情をたたえた表情へと変わっていきます。その変化こそが、木が生きている証です。ぜひ、経年変化を楽しみながら、木とともに過ごす豊かな時間をお楽しみください。

この素材は、東北地方の里山を再生しようという取り組みの中から生まれたものです。自然や環境保護を目的に、必要な木だけを選んで伐採する「択伐(たくばつ)」によって採取された鬼胡桃(オニグルミ)材を使用しています。また、伐採だけでなく、資材の輸送方法にも環境への配慮がなされています。たとえば、国内陸送(JR貨物とトラック輸送を組み合わせた手段)を採用することで、輸送による環境負荷の軽減を図っています。鬼胡桃材は、秋田から富山を経由して飛騨高山へと運ばれます。移動距離が比較的短いため、輸入材に比べて燃料使用量を抑えることができ、より環境に優しい素材であると考えています。

北海道および北東北から、自然環境に配慮した「択伐(計画的な選択伐採)」によって伐り出された、ナラやミズナラの木材(無垢材および突板)を使用しています。これらの木材は、日本を代表する銘木であり、大自然が育んだ美しさと力強さを備えています。その中でも、世界に誇るミズナラの素材をできる限りそのままの姿で活かし、これまでの表現とは一線を画す、深みのある質感を暮らしの中へ取り入れることで、自然と触れ合う時間をより豊かに、そして長く感じていただけると私たちは考えています。

ケヤキという木の名は、「際立った木」「尊く秀でた木」に由来するとされています。その風格と品格は、日本の木材の中でも最高級とされ、古来より神社仏閣や城の建築に用いられ、「神木」としても崇められてきました。しかし近年、環境の変化により、ケヤキも計画的な択伐が必要とされるようになっています。私たちは、そのような自然環境への配慮のもと、極めて限られた量ではありますが、選び抜かれたケヤキをあえて使用することにしました。

栗の木は、一般的に60〜80年で伐採の適齢期を迎えるとされています。材質が非常に硬く、腐りにくい性質を持つことから、日本では古くから建築材や家具材として利用されてきました。特に明治時代には、鉄道の枕木として使用され、日本の近代化を支えた重要な木材でもあります。現在でも住宅の土台として広く使われており、私たちの暮らしに欠かせない存在です。私たちが使用している栗の木は、秋田県を中心とした「奥筋(おくすじ)」と呼ばれる東北地方の山々で育ったものです。この地域特有の四季の気候を通して育まれた栗の木は、美しく多彩な木目を描き、ひとつとして同じものがない個性豊かな表情を見せてくれます。そんな奥筋の栗の木が、家具として新たに命を吹き込まれ、皆さまの暮らしの中に寄り添う存在となることを願っています。

イタヤカエデは、北東北の山地に自生する樹木で、樹高は15〜20mにも達します。秋には美しい黄葉を見せ、200種以上ある楓(カエデ)類の中でも代表的な存在です。葉がよく茂り、板で葺いた屋根のように雨を防ぐことができること、また葉の形がカエルの手に似ていることから「イタヤ(板屋)」という名がついたとされています。古くからこの木は、楽器材や「イタヤ細工」と呼ばれる工芸品の材料として親しまれてきました。近年では音の響きの良さが評価され、木製リコーダーの本体などにも使用されています。材質は硬く、透き通るような白い肌を持ち、その美しい外観から、高品質な家具用材としても知られています。導管が細いため、木目はやさしく柔らかな表情を見せますが、メープルシロップを多く含むため、木肌には特有の黒い点や線、そして「ガムポケット(樹脂痕)」と呼ばれる痕跡が点在することも、この木ならではの魅力のひとつです。

桜は、美しい花を咲かせることから、日本人にとって最も親しまれてきた樹木のひとつです。その木肌も、赤身と茶色が混ざり合った気品ある色合いで、とても美しく魅力的です。家具として使用された桜の木は、時を重ねるごとに黒味を帯びていきます。この経年変化が実に美しく、その過程を楽しむことができることから、桜は高級家具に用いられることの多い木材です。また、長く使い続けられる素材として、永年使用に適した家具材としても高く評価されてきました。持続可能な社会を目指す今、桜の木は、唯一無二の存在感を放つ、欠かすことのできない大切な家具材のひとつだといえるでしょう。
coating
木材と塗装のStory
世界には、木材の美しさを引き出し、耐久性を高めるためのさまざまな塗装技術が存在します。その中でも、日本で開発された塗料やコーティング技術の多くは、世界でも最高水準の品質として高く評価されています。この背景には、日本特有の四季折々の気候風土が深く関係しています。時代ごとに、気候や生活様式に応じた技術や用途が求められ、それに応じて多様な塗料や塗装手法が生み出されてきました。ときには手間を惜しまず、職人の技を尽くして仕上げる時代があり、またある時代には、効率性や耐久性を追究し、過酷な環境にも耐えうる塗装技術が進化してきました。私たちは、そうした日本の塗装文化と技術の歴史を尊重しながら、現代の塗装技術を融合させ、家具やコーティングの新たな表現を追究していきたいと考えています。

自然界から採れる植物由来のオイル(油)を使用し、木の表面の導管に染み込ませて仕上げる塗装方法です。表面に塗膜を形成しないため、木そのものの風合いをそのまま活かすことができ、触れた際には木肌の質感をより自然に感じることができます。ただし、塗膜がない分、テーブルなどで使用する際には細かな傷や、コップの水による輪ジミがつきやすいという特性もあります。しかし、その分補修は比較的容易で、木材本来の風合いを楽しみながら、長くご使用いただける仕上げ方法としておすすめです。
※メンテナンスセットのご用意もございます。こちらからお問い合わせください。

四季折々の暮らしに寄り添ってきた「柿渋」は、京都や奈良県で栽培された天王柿から抽出されたタンニンを原料としています。このタンニンに植物性素材を独自の技法で配合し、家具用のオイルとして仕立てています。柿渋には抗菌作用があり、古くから防腐剤や薬として、また寺院建築の耐久素材としても活用されてきました。さらに、漁網に塗布することで強度を高めるなど、その効果を活かした知恵と技術が受け継がれてきた、歴史ある天然素材です。この柿渋を、日本産のくるみ材に用いることで、さらに豊かな表情を引き出すことができます。くるみ材は油分を多く含むため、柿渋との相乗効果により、まるで古くから使い込まれたかのような深みのある風合いが生まれ、自然素材ならではの魅力をいっそう引き立ててくれます。
※メンテナンスセットのご用意もございます。こちらからお問い合わせください。

国内で家具に使用される塗料の中で、最も多く用いられているのが「ウレタン塗装」と呼ばれる技術です。塗装職人の技によって、決められた塗布量を均一に施すことで、高品質な仕上がりを実現することができます。ウレタン塗装は、表面にしっかりとした塗膜を形成できるため、オイル塗装に比べて傷やコップの水ジミなどを防ぎやすく、耐久性にも優れている点が特長です。一方で、塗膜が厚くなると木の触感が損なわれてしまうという側面もあります。そのため、私たちが四季折々の暮らしの中でご提案する「慶承の栗」には、耐久性を保ちつつも、木に触れたときのやわらかな無垢感や、無垢材本来の色合い・木肌の美しさを引き立てる、特別なウレタン仕上げを施しています。

漆(うるし)は、漆の木から採取される主成分「ウルシオール」に、乾燥剤や油などを加えてつくられる天然塗料です。その技法は古くから日本各地で受け継がれ、食器をはじめとする暮らしの道具の表面に塗ることで、私たちの生活に欠かせない素材として重宝されてきました。漆によって形成される塗膜は非常に硬く、かつ柔軟性にも優れており、近代的な塗料と比べても耐久性において優れた特性を持っています。酸・アルカリ・塩分・アルコールにも強く、さらに耐水性・断熱性・防腐性にも優れていることから、近年ではその機能性が見直され、改めて注目されています。しかし、漆を家具に施すには高度な技術と時間を要するため、非常に繊細で難易度の高い工程となります。私たち「四季折々」では、飛騨高山でつくられる“慶承”シリーズの中でも、特別な存在であるケヤキの家具にのみ、飛騨の漆職人の手によって漆を施しています。漆塗りの家具が生み出す特別な美しさは、時を重ねるごとに深みを増し、他の塗料では表現できない、唯一無二の味わいと風格を感じていただけることでしょう。
canvas
倉敷帆布のStory
leather